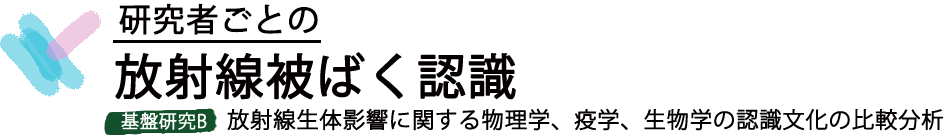研究者・専門家へのインタビュー(松田尚樹先生)
松田尚樹先生へのインタビュー 1/6
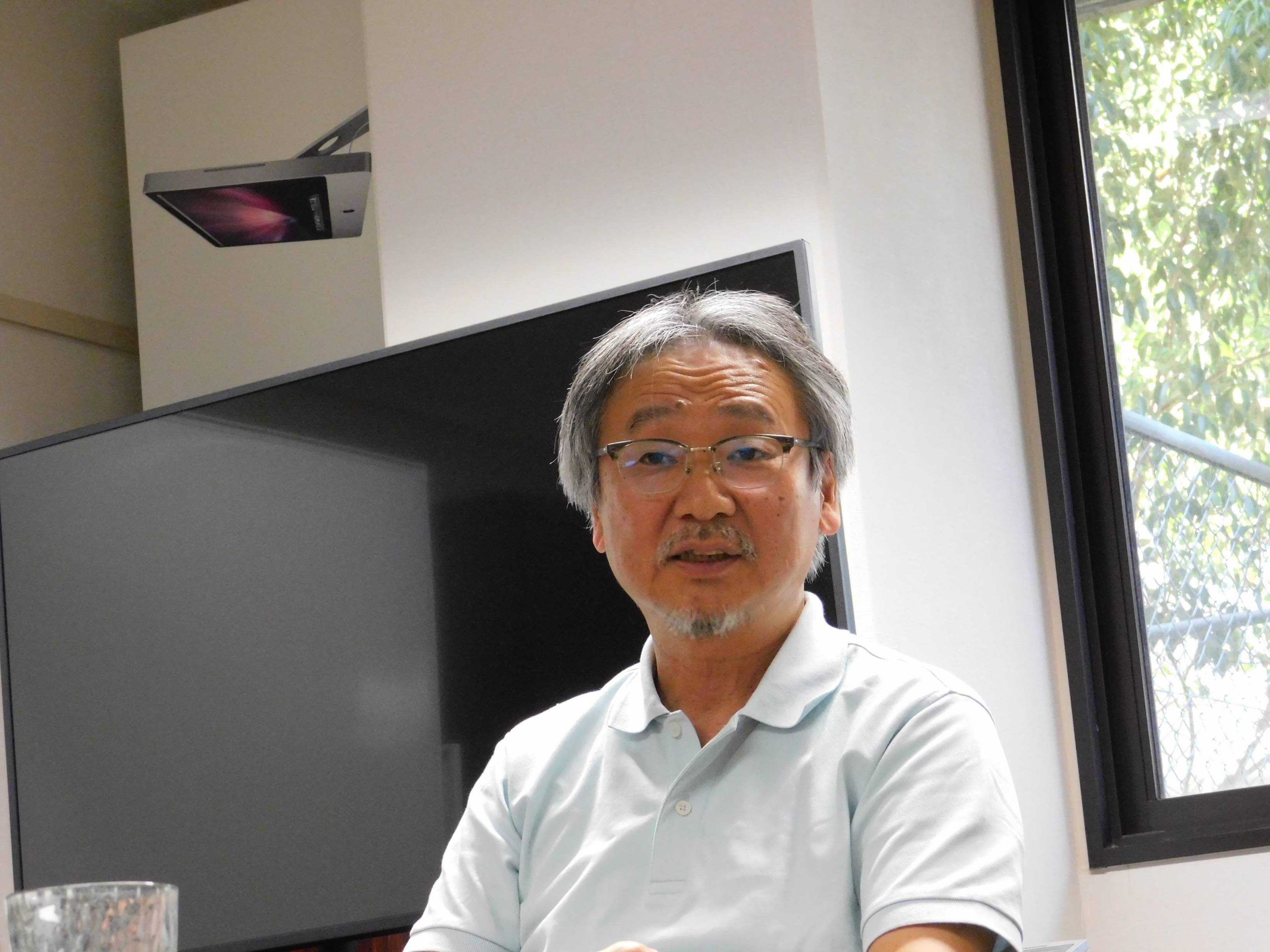
松田尚樹先生 プロフィール
専門: 放射線生物学、放射線防護、放射線教育長崎大学 原爆後障害医療研究所 教授
日本放射線安全管理学会元会長(現顧問)、日本アイソトープ協会放射線安全取扱部会副部会長、日本放射線影響学会学術評議員、原子力規制庁放射線審議会委員、人事院安全専門委員
1957年 神戸生まれ
序 研究者への道
角山: まずは先生の研究との馴れ初めからお願いします。先生最初は神戸でしたっけ?
松田尚樹先生(以下「松田」敬称略): 神戸ですね。僕は文系で商社マンとか国際金融とかがやりたくて、第一志望は慶応大学の経済学部で実際受けたんですけど、落ちました。
角山: 高校で理系選択とかはなかったんですか?
松田: あったけど私立の学校だったからそんなにね。慶応は当時数学とかもちゃんとあって、それを夢見ていたんです。けど失敗したので仕方なく金沢へね。なぜ薬学科というと、鎮痛剤とか飲むと頭痛いのが治るじゃないですか。あれがとても不思議でね。
角山: 先生それは高校の時点でその疑問をもたれていたんですか?
松田: そうです、だって不思議じゃないですか。
角山: それで大学行かれて、普通に薬学の道に行くんだという感じですか?
松田: 大学に入ったけど、まだ新聞記者の夢は捨てていなかったので、ほとんど学校行かずにね。またそっちを受けようと思っていたからね。でも気持ちだけで、大学に入ると麻雀とかそういう誘惑が多くて、だんだん勉強が苦痛になってきて、結局どっちつかずでそのままね。それで薬がなぜ効くかというのは、薬理学という授業があるんですけど、それに4,5回出ればほぼ原理原則がわかるので、「な?んだ」というかんじでしたね。それで分かってしまって、興味の対象が無くなってしまった時に、丁度、分子生物学の授業があって、1978年ぐらいですかね、岡崎フラグメントとかの話を聞いて少しまた興味がわいてね。
坂東: 大学におられた時点ではすでにDNAは発見されていたんですね?
松田: そうですね。分子生物学、生化学とかですでに出ていましたから。高校時代はメンデルとかがせいぜいでしたね。大学では、トリプレットとアミノ酸の配置は全部わかっていて、原核細胞から真核細胞に移っていって、その大きな違いというのはヒストンがあるかないかなんですよね。ヒストンがその時の主流で、僕の居たところの下の階では、丁度ヒストンを研究していましたね。そういう時代ですね。ぼくはそのとき放射線生物学をやっていましたね。
角山: もうそのときには放射線生物学をやっておられたんですね。すると、なにかに放射線を当てて影響を見ていたんですか?
松田: そうです。当時はHeLa細胞とか白血病の細胞とかで、放射線と紫外線を両方やっていて、僕のテーマは実は紫外線だったんですけど、要は何をエンドポイントとして見るかというと、DNAが損傷するメカニズムはある程度わかっていたんですね。紫外線だったら除去修復とか。
角山: なるほど。ではピリミジンダイマーとかもですか?
松田: もちろんです。ただ解析の手法が遺伝子レベルのPCRとかもないし、ノーザンブロットもサザンブロットもないし、だから遺伝子発現からタンパク合成の段階で見る手段がなかったんです。ただ修復するということは分かっていたんです。まあそれも大きなダメージで無いと見れなかったんですけど。
角山: それは生存曲線かなんかでマーカーを見ていたんですか?
松田: いいえ。それはスクロースグラジエント(ショ糖密度勾配遠心法)というので見ていました。DNAを高線量で放射線とかX線とかを当ててやると、ブレイクがたくさん出てきて、つまり分子量が小さくなりますよね。それでスクロースグラジエントで超遠心分離機を回して分子量の違いで見るんです。それでDNAをRIでラベリングしておいてそれぞれのRIを測っていったらどの辺の分画に一番たくさんDNAがあるのかがわかると。それでも、検出限界は下が10グレイとかでしたよ。今だったらその辺も今もう進化していて、抗体をつかってすぐ分かるじゃないですか。その次に僕がテーマでやったのがアルカリ・エリューションっていって、DNAをアルカリ溶液にさらすと弱いところが切れていくんですよね。それで遠心では回さずに、0.2マイクロメートルのフィルターを通すと、小さいモノから早く流れていって、これだと2、3時間ほどでできてしまうので、それをやっていましたね。そういう時代です。
坂東: 放射線の生体影響を調べるというのは、かなりそのころから全国的にあったんですか?
松田: 多分今よりもあったと思います。当時のわたしの研究室は堀川正克という教授だったんですけど、大阪大学の遺伝学教室のご出身でした。その後、京都大学の放生研(放射線生物研究センター)の助手でおられて、そのあと金沢に来られたんですね。堀川先生は実は私がM2(修士二年生)のときに亡くなられたんですけど、その後、当時の放生研で助教授をされていた二階堂先生がうちの教授で来られたというそういう流れです。
坂東: じゃあ、ご専門ははっきり放射線系ですね。日本でそういうところはそんなにはなかったですか?
松田: 京都大学の放生研ができる前に、医学部に放射線基礎医学という教室があって菅原努先生の一派がやはりあちこちに教授を輩出されていますので、今でも残っているところもあります。
角山: 菅原先生のところの分子生物学的な分野の一派はあったんですかね。あまり聞かないですよね。細胞レベルではやっていたのかもしれないけどDNAできちんと解析するというのはまだ先端のレベルだったんですかね。
松田: そうですよ。修復反応を見ようと思っても、例えばタンパクの分子レベルで見れる手法が無かったし、ましてやリン酸化するとか発想もなかったですね。だからあのころは乱暴なやり方で、とりあえず修復はするみたいだと、酵素はこういう酵素活性が必要みたいだと、それぐらいまでだったんですよその時は。かたや放射線の影響で、癌そのものがよくわかっていなくて、当時はインビトロで、正常細胞を癌化させるというのが、アメリカのマーハーの一派と大阪大学の門永先生という、このひとは理研です、それと川崎医大の難波先生、そこしかできなかったんですよ。
坂東: そうすると日本は当時結構がんばっていたんですね。
松田: ただ、一般化してなかったんです。というのは、血清を使うということで血清のロットによってぜんぜんデータの出方が違っていたんです。まだ当時はね。それから細胞も初代培養でヒトから取ってくるんだけど、普通は胎児から取ってくるんですよ。今はなかなかできないですけどね。ぼくも胎児の肺の細胞を使っていたんですけど、5ヶ月目ぐらいのかな。それがやはり細胞によって違っていたんで一般化しなかったんです。そういう細胞を使ってなにをエンドポイントにするかというと、癌化させるのはなかなか難しいから、ミューテーションを見ようとか、6-チオグアニンや8-アゾシトシンのポイントミューテーションをみようとか、それぐらいしか当時はなかったんです。だから癌直接ではなくてですね。
坂東: 今でもまだミューテーションから癌までの機序はわかっていないですよね。
角山: 当時は、ビッグラボみたいなかんじでボスがいて准教授か助手がいてドクターがいてというような感じですか?その最初のテクニックは先輩から教わったんですか?
松田: そうですね。堀川先生がおられて、後に教授になる二階堂先生がそのころは講師でおられたんです。それから講師で鈴木(文男)先生といってその後広島大学の原医研(原爆放射線医科学研究所)の所長になられて、今はもう退官されていますけど、その人がおられて、さらにその下に京大のあの強烈な渡辺先生もおられました。とても厳しかったですよ、人間性を破壊されるような厳しさでした(笑)。
坂東: 一日にどれぐらいの時間、実験をやっていたんですか?
松田: 細胞の実験なので24時間ですね。細胞周期というのは当時からわかっていたので、細胞周期を止めてそこから同時にスタートするんですけど、だから何時間後に放射線を当てるんだというような実験がどうしても入ってくるわけですよね。どのフェイズで当てろみたいにね。そしたらもう24時間ですよね(笑)。
中尾: 厳しいというのは仕事量的に厳しいというのと、他にどんなことが厳しい理由としてありますか?
松田: 仕事量的にはね。まあ厳しかったんですけど、それは楽しくやっていたんですね。セミナーとか雑誌会とかあるじゃないですか、そこでぼろくそに言われて人間性を破壊されるようなね。どっちが指導しているんだと思うけど、こっちが100%責任をもってることになるんですよね。あそこまでぼろくそに言われるのはめずらしい、女の子はもう涙でしたね。今ならできないですよ。アカハラですね。
坂東: ボロカスというのは、リーズナブルなボロカスなんでしょ?
松田: もちろんそうなんです。まあやっぱりこっちが不完全だったんでしょうね。まあぼくが一番怒られたのは「適当に答えるな」というところでしたね。わかっていることと分かっていないことをしっかり区別しろということですね。でも何も答えないともっと怒られるからね。理不尽な話や(笑)。