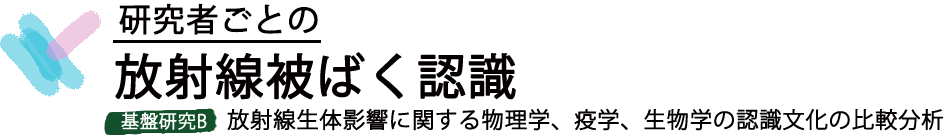研究者・専門家へのインタビュー(和田先生)
和田昭允先生へのインタビュー 前編 4/4
東京と京都 生物学への思い
b:うるさいですわ、そりゃ、で、物理の人は、どうしても自分がなぜ興味を持ったか、自分の物理の経験から一定の思いがありますからね・東大の歴史と比べて、京都での生物物理を作った経緯は、ひょっとしたら、また、違う動機があったような気がするのです。
w:そうですか。
b:京都大学で生物物理教室を立ち上げるときの議論・・実は今年50年になるのですが。1960年後半といえば、いわゆる大学紛争の真っただ中で、ちょうど私も京大の助手でした。当時学生たちは「古い体質を叩き潰す」と意気込んでいました。京大の物理教室は講座制を廃して新しい分野を開拓するという意気に燃えていました。学生(大学院生も半分は当時の所謂「大学解体」みたいな主張に親近感を持っている時代でしたねえ)との討論会で、福留秀雄さんが、「古いものを乗り越えて新しいものを構築するってことはどういうことかわかっているか?この物理教室では、古い学問を乗り越えて、新しい領域に挑戦している怒涛のような世界の流れと呼応して研究をしている。進歩というのはそういうことなんだ。なにも、暴力をふるって破壊することではない」みたいな迫力のある大演説をされていました。私はこの時の福留さんの迫力に圧倒されたのを覚えています。当時、新しく生物物理学会を創設するというので、物性専門の寺本英先生(テラポンといってみんなに愛されていた愉快な先生でしたが、はりきっておられました。先生もきっとよくお付き合いされたと思いますが)を先頭に、どういうイメージでどんな学問を構築するかというような熱い議論を、湯川先生をはじめとして戦わせていたわけです。その意気込みと迫力がありました。ちなみに、理学部は暴力学生に占拠されることはありませんでしたね。理学部の先進性に多少は敬意を表したのかもしれません。 話がそれましたが、そういうわけで福留さん(湯川研究室の5年先輩で、素粒子出身でした)は、シュレディンガーやデルブリュックに刺激を受けた世代ではなかったかと想像できます。実は、そういう系譜があって・・・・・
w:寺本英さん、テラポン―懐かしいですね-。
b:繰り返しのない秩序というのに非常に興味を持っておられたことは同じでも・・・放射線生物ってのは、あまり影響を与えていない・・・。
w:違いますね、僕の知っている放射線生物学は玉木英彦(注:1909-2013年仁科の研究室だった)という先生です。何かねぇ、実用学から入ってきた放射線生物、まあ、放射線防護学ということで、特にビキニをきっかけに放射線防護の話と結びついていました。
b:なるほど、学問的今日好奇心というより、放射線防護という実際社会問題と結びついた方向とはちょっとニュアンスが違いますね。確かにマラー達の実験も、遺伝の話と結び付いて、被ばくによる遺伝的影響があるかないかで、ワーッと盛り上がり、放射線防護の方向へ行くわけですね。確かに、この経緯を見ると、やっぱりモチベーションが、違うんですね。
w:そうかもしれませんね。ちょっとその辺よくわかりませんけど。
b:いや、物理学者が興味を持ったのは、コペンハーゲンのボーア研究所に行かれた仁科先生ですが、帰国して加速器を運転し始めたとき、「これを、ネズミに当てて実験しろ」と言われた(村地孝一が実施)。やっぱり、影響を受けてはいるのですが、この話ほとんど原子核実験の方も知らないです。この実験を実行した村地さんたちは、放射線生物を続けてはおられたようですが。ですから、ここに何かあるという雰囲気、これで何か分かるかもしれないという期待はあったみたいですねぇ。
w:そうですね。うん。新しいものが出てきたっていう感じがねぇ、続々とありましたから、そういう意味では今の人はかわいそうだな~。
b:そうですね、すごい時代だったのですね。確かにデルブリュックは、それでファージの研究に熱中するわけですね。でも、どうも、私はシュレディンガーの考えたような新しい法則があるのではなくて、やっぱり物理法則でいけるのだと、その後のg発展は物語っているように思います。特に、ワトソンやとクリックの論文が決定的だったのですかね。ただ、お話を聞いていると、それだけじゃなくって色んな面で生物の神秘を解き明かしたいということですよね。やはり生物は物理とは違いますね。
w:違いますね、ハーバードへ行ったのは、54年から56年ですけど、そのときに私の先生のドティさんが、ワトソンクリックと仲が良くて、今度こういうDNAの二重らせんモデルが出来たんだよって僕に教えてくれた。
b:ちょうどその頃ですか、なるほど、だから、物理化学的なメカニズムである程度、分かるんじゃないかという、確信みたいなものがあったのかも知れませんね。
w:みんなそう思ったらしいですね。湯川先生もそうだったですね。あのねぇ、有名な話があって、湯川先生も、生物の中にそれこそほんとに、中間子論みたいなものが出てくるのじゃないか、位のことを思っておられた。それで、結局ねぇ、湯川先生に言われたって言うんですよ。「そういうものがあるかと思っていると、何のことはない、結局、積木じゃないか」とね。大沢文夫さんから、直接聞いたからこれ間違いないですけれども、
b:つまり、物理・化学である程度、解明できるんじゃないかと、そういうことですよね。
w:そうです。積木、素子がみんなもう分ってて、ただ、それが色んな格好で積まれてるだけじゃないかと、言われたって、大沢さんが言っていましたね。まさにね、その通りだと思いますよ。えぇ。
b:なるほどねぇ、素粒子論も、1960年代、わーとたくさんの素粒子が見つかって、それを解明しようと思っても、発散の困難とかもでてきて、「場の理論」という基本的な枠組みはどうせ使えないのじゃないか、どうせ、素粒子の中までこんな理論ではいけないと思った時代があります。そうすると、中に入り込むのを諦めて、外からうかがい知ることで満足しよう、そういう考え方(Sマトリックスセオリー)が出てきたのです。構造を解明するのをやめるわけですから、まあ、お茶を濁すというか、中のほうはカオティックでどうしようもない、というような話になって。
w:それは、何年頃ですか?大体。
b:1960年代です、
w:60年代
b:あの~、加速器が動き出し、たくさんの素粒子(ハドロン)が次々見つかって・・・。素粒子の解明には、場の理論とかは使えない、そこはもうブラックボックスなのだ、といいうわけです。しかし、1960年の終わり頃から、フェイズが変わりました。
w:わかりました、ああそうか。
b:で、場の理論が復活するわけです。理論も整備されて、素粒子論が復活したわけです。私は当時、この続々とでてくる素粒子に魅惑されて、現象論から入って、どう分類するかといった仕事をしていたのですが、新しい潮流は、突き進んでワインバーグ・サラムの標準理論へと突っ走るわけです。すごい時代でした。
w:東大では、どんな連中がそれやっていたのですか?
b:東大は、岩崎さんとか荒船さんとか、そういう若い人たちですね。ちょっと上の世代は、Sマトリックス派が多かったです。特に東大は。それに反して名古屋は坂田学派といった風に様々でした。でも、見る目のあった人は場の理論を早くからやり始めていました。で、結局、何が成功したかといいますと、結局、中へ入って、そのメカニズムを解明するというやり方、諦めずにやったほうが成功したのです。
自然は結構、律儀にできているのですね。わかってみれば簡単・・・。
w:あ~、そうですね。このへんで、ちょっと、お茶を飲みましょう。
対談日:2017/4/27
インタビュアー:坂東昌子
» インタビューサイト トップページ