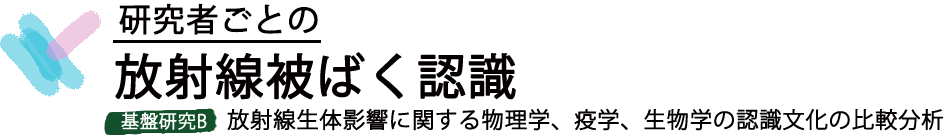研究者・専門家へのインタビュー(山下俊一先生)
山下俊一先生へのインタビュー 4/5
アメリカでの研究生活
中尾 その大学院を辞めて病院の方にもどって、アメリカに行ったという形ですか?
山下 そうです。3月31日で満期修了退学をして、その前にお話をいただいていたのかなー、6月にアメリカに行きました。
樋口 それは甲状腺の関係で?
山下
いいえ、全く関係ないです。話がちがうんですよ。甲状腺の所に行くのかと思ったら、シュロモ・メルメッド(※1)という、今でこそ下垂体のトップですけど、当時はどこの馬の骨かわからんような、シーダー・サイナイ・メディカルセンター(※2)といって、ロサンゼルスの有名なユダヤ系の病院なんですけども、南アフリカのケープタウン出身で、イギリスで学位を取ってアメリカに来たばかりの新進気鋭のやつがおると。まあ、海のものとも山のものともまだ分からんけどもと。
当時はソマティックハイブリダイゼーションといって、私は留学する直前にモノクローナル抗体を作るハイブリドーマを作っていたんですね。ハイブリドーマは血液細胞とミエローマ細胞をくっつけるんだけれども、これに対して体細胞、普通の細胞とミエローマ細胞をくっつけて、今で言う再生医療のはしりですね。それをしていたんですね。それで私はソマティックハイブリダイゼーションという手法を学びに行けと言われて、行ったらこれまた面白いんで、1984年の7月からオリンピック、ロサンゼルスオリンピックが始まる。それで、ボスいないんですよ。
※1 Shlomo Melmed
※2 Cedars-Sinai Medical Center
中尾 オリンピックを避けて!
山下
そう、ユダヤ人はターゲットになるというんで。それでロサンゼルス空港とシーダースとハリウッドはターゲットになるというんで、それで関係者らがいない!
そしてソマティックハイブリダイゼーションもやめたと言うんですよ。これから分子生物学というのは遺伝子だとかいうんですよ(笑)。
中尾 すごいですねー。
山下 それで私は、右も左もわからないですよ。ボスもいない。
坂東 それでも、その当時に分子生物学を始めたいうのはすごいことや。
山下 ちょうどシティ・オブ・ホープ(※1)に板倉先生(※2)とか、一次構造が決定されていたインシュリンを大腸菌で作ったちょうどその時だったんですね。あのボスは偉くて、インシュリンの生物的な影響をー当時ハーバードに春日先生とか素晴らしい先生がいたんだけどーそういう仕事がちょうど時流に乗る頃なんです。で、いわゆるノーザン(ブロット)」とかサザンとかウエスタンとかそういうことをそこで学んで。
※1 City of Hope National Medical Center
※2 板倉啓壹 シティ・オブ・ホープで1978年大腸菌を用いたヒトインスリンの作成に成功
中尾 最先端の…
山下 そうですね、今で思えば当時は最先端だったんですね。
中尾 そういうことに臨機応変に対応していかれたんですね。異分野交流ですねまさに。
坂東 そんな人はめずらしいでしょうね、医学では。いったん決めたら一筋に。
山下 そうですね。たいていは一つにテーマを決めて動きますからね。
家族と暮らしたアメリカ社会
中尾 そこでやはり視点とか視野が広まったというふうにお考えですか?
山下 というよりも、一番私が留学してよかったなと思うのは、ユダヤ人のコミュニティと一緒に生活、仕事したことですかね。毎週金曜日にはサバーといって聖金曜日ですから土曜日にかけてー彼らは土曜日は仕事しないんですけど―うちのボスもそうで、論文を書くときも必ず家に呼ぶんですよ。で、金曜日はお父さん(家長)が中心でキュッパをかぶって、旧約聖書やタルムードを読むんだけれど、その中でびっくりしたのは、「われわれ4000年の迫害の歴史だ」と、子どもたちにその話をするんです。自分たちが唯一子供たちに教えられるのは我が民族ユダヤ教の精神だと。おお、こんな教育を子どもたちにしているユダヤ人というのはすごいなと思って。そしてある時、息子さんが13歳の時に、今は医者になっていますが、バル・ミツバといって成人式をするんです。この成人式に世界中から親族郎党が集まるわけです。そして、シナゴーグで蕩々と話をするんですよ。自分の意見を。あることわざとか事象に対して自分はこう思うと。これを聞いていて、とんでもない民族だと思いましたね。ジューイッシュのコミュニティで―うちの子どもたちも全部ジューイッシュスクールに行ったんで、みんな友だちはジューイッシュなんです。そしたらですね、教育がはんぱじゃない。普通の詰め込みじゃないんですよ。芸術からスポーツから、そういうのに全部お金を使うんですね。なぜこれだけ音楽の才能ある人が多いかというと、そういうふうなものへのチャンスをきちんと与えているんですよね。子どもたちはそれを選択するんですよ。
坂東 芸術家、科学者、みんなものすごう多いですもんね。
山下 私が3年間で最も学んだのはユダヤ人の世界を垣間見たと言うことですね。
中尾 日本人で、すぐにそこのコミュニティーに受け入れられてもらえるというのは、なかなか珍しかったんではないでしょうかね。
山下 どうでしょうかね。
樋口 当時は日本人の方というのは、あまりいなかったんですか?
山下 当時は360円から250円になったころかな、1ドルが。それでもう、うちの家内も子どもたちもみんなアメリカが気に入って、残ろうと言っていたんですよ。私も残ってもいいかなと思ったけど、父親が病気したので帰らざるをえなかったんですけど、3年いて嫌な思いは一つもなかったですね。
中尾 人種差別を受けたようなことは…
山下 むしろロサンゼルスでよかったなと思うのは、ハンコック・パーク・スクール(※)という小学校に子どもたちはみんな行ったんですけど、そうするとそこはメキシコ人とか黒人とか貧困層がいっぱいいるんです。ところが子どもたちはアメリカにきたらみんなアメリカ国民なんです。親が違法移民であっても。そうすると学校で貧しい人たちのために朝ご飯を出すんです。だから自分の息子がなぜ朝早くから「学校に行く行く」というのか、おかしいなあ、日本じゃ全然行かなかった子がね、変だと思ったら、ご飯を食べてた、朝ご飯を(笑)。私、大したものだと思って。
※ Hancock Park Elementary School:ロサンゼルスの公立小学校
樋口 アメリカだと低所得者層向けの…
山下 うちの子どもは低所得者の子(笑)。そこで子どもたちはものすごく自由に育って、夏は野球でしょ、春夏は水泳でしょ、冬はバスケットですよ。そのバスケットに家内がいつも子どもたちを連れて行ってね。一回家内が行けんから連れて行ったらですね、ダウンタウンの暗いところに行って、黒人ばっかりなんですよ。私は怖いなと思ったんだけど、子どもたちはもう一緒になってる、黒人と。だからうちの子どもたちは頭はよくないんだけど、そういう偏見とかまったくないんです。むしろ日本に帰ってきて、子どもたちがカルチャーショックね。まず、学生服でしょみんな、小学校。これがまず驚きの種。そしてうちの子どもたちがびっくりしたのは、みんな朝礼をして体操しよる!(笑)
中尾 それはカルチャーギャップがありますねえ。
坂東 いくつだったんですか?
山下 当時、5・3・2歳で行って、帰ってきたのは8・6・4。だから本当はアメリカに置いとった方がよかったのかも知れませんね。日本の変なね、また…
日本の医学界に戻る
中尾 やはり日本に帰ってこられて、先生ご自身も日本の医学の中で何かのカルチャーギャップというのは?
山下 一番感じたのは、年功序列でしたかね。やっぱり特に医者の世界というのは外科系でもそうですが、内科系でもそういう傾向があって、やはり順次性を大事にしますから、若い人が上に立つというのはあまりないんですよ。それはそれである意味いいんですけど、いろんな弊害もあって、アメリカのスピードに対して日本はやっぱり遅い。私は幸い長瀧先生の指示でアメリカに留学して、長瀧先生の指示で戻ってきて、長瀧先生から臨床で分子生物学をきちんとというのでラボを作って、若い人たちを留学させて、だいたい体制が2年間でできたんですね。これでもうお礼奉公おしまいだと思って、関連病院に出たんですね。成人病センターというところに。それでやっとこれで大学のヒエラルキーから外れて自由にできるかなと思ったら、原研(※)の教授選考があるから、おまえはノミネートされているみたいだから、教授選に出ろと言われて、それで原研、つまりここに来たのがまた運命の分かれ道。1990年でした。
※ 長崎大学原爆後障害医療研究所
坂東 そうすると、チェルノブイリが86年。
山下 チェルノブイリはその時はまだ私関係していませんでしたから、まったく。
中尾 チェルノブイリの時はいらっしゃらなかったんですか、まだ。
山下 アメリカです、84年から87年まで。
坂東 長瀧先生は?
山下 その前からかもしれませんね。重松逸造(※)先生が87年にアメリカに呼ばれて行ってからですから、長瀧先生は87年か8年からは関わっていたはずです。
※ 重松逸造 金沢大学医学部教授、放射線影響研究所理事長等歴任