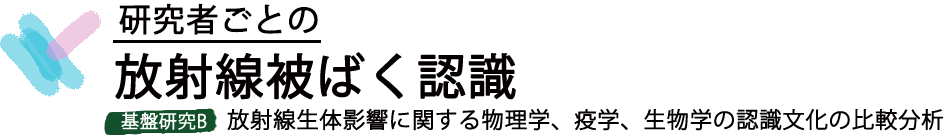研究者・専門家へのインタビュー(澤田哲生先生)
澤田哲生先生へのインタビュー 第1回 5/5
分野横断的つながりと原子力
坂東 考えてみると、やっぱり、湯川先生が偉かったのは結局分野横断型をエンカレッジしたからだと思うんですよ。そのへんはどうですか?
澤田 その通りだと思います。湯川さんに限らず、最初に原子力を立ち上げた大学は残念なことに今や似たりよってたりで、衰退しています。存亡の危機の崖っぷちにある。真っ先に衰退したのが東大でしたね。
しかしね、東大原子力工学にしても、京大の原子核工学にしても、創成期は全学をあげて分野横断的にやろうという意気込みは凄かったのですよ。ところが、現状を見てみると、もう50年ぐらいたってますけど、まったく分野横断的じゃないんですよね。むしろ逆行している。ムラもムラ。数多ある学者ムラのなかでも劣化が最も著しいように見受けられます。
坂東 東大の最初の人ってだれですか?
澤田 向坊(※)ですよ。向坊さんたちは分野横断的でやろうとしたんですけど、工学部が工学部単体で原子力工学をやると言ってそっちにいってしまったんですよ。工学部が原子力を囲ってしまったようなものですね。そして他分野との連携にはなんら関心を示さないようになっていった。どこの大学も似たり寄ったりなのですが、原子核工学や原子力工学の創成に尽力した先生方には大物が多くて、学長(総長)や学術会議の会長や学協会長になった人が多い。そこに繋がっているからか、どうやら天狗になっているような傾向が見られますね。ある種の聖域。結果、他分野からの人材導入にあまり積極的ではなかった。まあ、分野横断的な視点からは、何人も招き入れようとしなかった。他分野からはムラのように見られ遠ざけられた。3・11までは、原子力ムラの構造に安住できた・・・それは紛うことなき真実ですよ。なおかつこのムラには地位と予算と利権があったから、いっこうに世間を気にする風がなかった。その挙句が3・11で、一気に瓦解した。でもまだそのことに気がついていない向きもあるような気がしてなりません。
※ 向坊隆 応用化学者、元東京大学総長。日本原子力産業会議会長などを歴任
坂東 澤田さんが、「原子力ムラの構造」を科研費で取り上げたのも、そういう村はずれにいて、これでは次がないなと感じたからですよね。東大では、電気と、何が中心になったんですか?
澤田 機械ですよ。物理は正面からは入ってないんですよ。物理系の人は入っていますがね。最初は、向坊さんは電気なんですけど、電気化学というかそれは少しは融合分野みたいなものですよね。途中から分野が狭くなってね。だからとにかく、原子力工学、原子核工学はたんなる分野の寄せ集めにしかならなかったんですよ。だからグランドデザインを持った人間が育っていないんですよ。分野の寄せ集めではテクノロジーに対峙して前へ進むことがない。
坂東 確か、そこで育った方の中に、故北澤先生(※1)も向坊先生のところで、トリウム溶融塩炉に当初取り組んでおられたと聞きましたが、当時は未来を夢見る優秀な若者がたくさん原子力の未来を夢見て専攻したということですよね。さっき触れられた湯川さんらを軸にした総合原子力研究機構(※2)・・・そういう分野総合的な仕組みを作りたかったわけでしょ?確かホリバの会長、故堀場雅夫さん(※3)は助手で入ってたんでしょう?
※1 北澤宏一 化学者、東京大学名誉教授。元東京都市大学学長・独立行政法人科学技術振興機構顧問、高温超伝導研究の第一人者。北澤先生の言「大学の研究者は“研究は自由にやりたい”という意識を有する。この意識がない人は研究者に向かないと私は思う。しかし、力のある研究者は“社会の付託に応える研究”にも食指を動かすように思う。」
※2 確認中
※3 堀場雅夫 株式会社堀場製作所創業者、京都帝国大学理学部物理学専攻卒
澤田 今の堀場社長のお父さんですね。堀場雅夫さんは、当時理学部の助手で、湯川さんの立ち上げの初期構想に関わっているんですよね。荒勝さん(※1)の流れですね。それから荒木源太郎さんが化学研究所にいたんですが、これは化学者として名高い喜多源逸(※2)の思惑があったようです。喜多源逸は、京大の化学研究所の所長であった戦前の頃から化学に量子力学を取り入れることの重要性に早くから気がついていた。そこで湯川さんを訊ねて適切な学者を問うたようです。湯川さんが荒木さんを推薦したということだと聞きました。
※1 荒勝文策 物理学者、京都大学名誉教授
※2 喜多源逸 工業化学者、京都大学化学研究所長や浪速大学(現大阪府立大学)初代学長などを歴任
坂東 面白いですね。その辺の歴史を調べると、ほんとうはそういう分野横断をもっと広範囲にやりたかったけど結局できなくて、原子核で言えば工学部の中にちょこっと理学部が入ってきただけに終わってしまったんですね。原子核工学の中に素粒子理論が入ってきた。それはしかし分野横断的な展開にはならなくて、ちょっと無理に接合したイメージに過ぎなかった。
澤田 だからですね、単なるエキスパートエンジニアになってるんですよ。サイエンスとエンジニアの融合がまずあって、さらにその先に行かなければいけないのに、つまりテクノロジー的になってないんですよ。テクノロジーが大切なのに、エンジニアの寄せ集めで、そこにちょっとサイエンスが入ってるぐらいでとどまってしまっている。
私は、物理をそもそも志していたのでサイエンスのものの見方のエッセンスは心得ていると自負してますよ(笑)。そして、就職して工学つまりエンジニアリングの世界に体を突っ込んだんですね。ものの考え方の違いにカルチャーショックを受けて結構悩みました。しかしそのおかげで両方の世界、両方の価値観の違いを知ることができました。さらに、その後テクノロジーと名のつく大学にきて、テクノロジーとは何かということを考える羽目になってしまった。
東京工業大学って英語ではTokyo Institute of Technologyなんですね。私がまずはじめに疑問を抱いたのは、「工業」と「Technology」は別物だろうということです。両者の違いというか違和感に向き合っている人は実は意外に少ないのではないかと感じています。
坂東 改めて聞きますが、テクノロジーとエンジニアリングとはどう違うんですか?
澤田 そう来ましたか。一言で言うと、テクノロジーは大昔からあるやつですね。人間がサルからヒトになるときにはテクノロジーの作用があったわけですよ。テクノロジーの進化圧にうまく乗っかったヤツらがサルからヒトになったとも言えます。その筋の科学者によると、親指の回転軸が変わったことがポイントらしいですよ。チンパンジーは親指も含めて樹にぶら下がるのに便利な一方向にしか動かない。まあ木の実をつまんだりはできますがね。人間の親指の回転軸はサルとは違って、もっとグリグリ回るではありませんか。つまり動作の自由度が増した。サルよりもずっと器用になったんです。それで物作りを始めたんです。親指の回転軸の自由度が増したのは、ヒトの祖先が樹から降りて二足歩行を始めたからだというのです。
坂東 なるほど、物作りというのがテクノロジーですか?
澤田 テクノロジーは宇宙の進化を駆動しているものです。その結果として、ある意味必然的流れとして、ものづくりがありイノベーションがある。テクノロジーの一つの断面が現実に顔を出したのがものづくりなのでしょうね。
私が3・11後、TVに頻出していた頃、番組の合間に担当常務とよく雑談をしていたんですね。そんな時に私が『ぼくたちの身体も放射線でできているんですよ。放射線の凝り固まったようなもんです』といったらバカを言っちゃあいけないと目を丸くしてました。
板東さんを前に言うのもなんですが、宇宙の始まりの直後は放射線しかなかった。そこからやがて放射線をいわば素材にして物質がつくられて行った。放射線ドミナントな世界から物質ドミナントな世界に転移した。その次は約40億年前です。情報が現れた。デオキシリボ核酸(DNA)であり二重螺旋ですね。物質を素材に情報が生まれたのです。ここでいう物質とは、典型的には様々な元素の組み合わせで生まれたA(アデニン)、G(グアニン)、C(シトシン)、T(チミン)などをさします。そしてどうやら物質ドミナントの世界から情報ドミナントな世界に転移した。テクノロジーの大本、根幹にはこのような遷移があります。サイエンスやエンジニアリングのこのようなテクノロジーのある種の進化の中で起こったことなのだと思います。ではそのような進化を起こしてきたメカニズムあるいは進化圧とはなんなのでしょうか。それ自体がテクノロジーだという言い方もできるかもしれません。
だからサイエンスやエンジニアリングは、テクノロジーのもとで一つの知恵袋のようなものでありツールボックスの役割をしていると言えるのではないでしょうか。サイエンス的なもの、エンジニアリング的なものを駆使してテクノロジーが発達する。だからこのまえ松田さんもおっしゃっていたけど、テクノロジーの断面で見れるんですよ。農業革命から産業革命へと変化して行った。なぜ変化したかは実は誰もきちんと説明できないではありませんか。。そこから情報に変わってきて、コンピューターに変わってきてね。チューリングが計算機の可能性を論文にしたのが1936年。シャノンの情報理論は1948年ですね。それとほぼ同じ時期に最初のコンピューターENIACが完成しました。そして情報革命によって人間の脳をコンピューターと同期するようなコンパクトな脳のネットワークを作る。そういう物の変遷はやっぱりテクノロジーのもとの進化圧がなせるところなんだと思います。そこにサイエンスとかエンジニアリングが入ってくるんです。だから原子力はまさにテクノロジー的な観点からの一つの相変化があってしかるべきなんですけど、相変わらずエンジニアリングの寄せ集めなのではないでしょうか。だから、3・11後の事故対応の拙さはそういう〝欠如〟の表れですね。そしてそれは今も今後も続いていくように見えます。
坂東 全体像が見えてないからね。自分の所しかわからないんですよね。だから、なんかその辺りの分野横断的というかもうちょっと総合的な視野があると、次の打つ手に繋がると思うのですけどね。放射線防護もなんか、視野が狭いですね。
防護というのは規制というルールをいかに守るかに終始しすぎて、ルールを作った科学的基礎についてはほとんど何も考えていないような気がします。防護の人は科学者というより、法律を守るためにどうしたらいいかというテクニックだけを取り扱っているのはないかと…つい思ってしまいます。じゃあ、原子力にテクノロジー的な視点を持ち込むのにはどうしたらいいのかなあ。
科学と社会
澤田 最終的に出口って、市民とか社会でしょ?アカデミア、特に原子力はねえ、市民とか社会との付き合い方を知らない。学の中で終わって、1ミリシーベルトにしても人々は相場観が欲しいはずなんですよね。そこをどうするかという出口というかインターフェイスというか、そこが非常に重要になってくるんですけど、その分野横断的になると、社会科学的な視点がどこかで入ってくるはずなのです。社会科学との間に現状あるギャップに挑まなくてはいけなくなるはずで、す。ところがサイエンティストとエンジニアが狭い分野領域に自己を閉じ込めてしまうと、社会との接点なんぞ必要ないじゃないですか。サイエンスはこれが正しいというモデルを作る、理論を実証するというのが最大ミッションですよね?エンジニアリングは物作りだから、社会との接点は必ず出てくるんですけど、原子力に限って言えば実に自己満足的な物作り志向が多いわけでよ。一つの幻想としてね、良い物を作れば自ずと社会は受け入れてくれるっていうのがあるけど、これはほとんど間違いなんですよ。社会にプロアクティブに訴えかけていかないと社会に認知される物にならないですよ。例えばビデオを例にとりましょう。かつてVHSとβという二つの方式が並存してあった。βが圧倒的にクオリティーが高いわけですよ。しかし市場競争に負けたんですよ。それは社会に対する情報共有ができなかったのみならず、プラスαで様々な淘汰されるべき要因があったはずなんですよ。
坂東 まあそういえばマイクロソフトもそうですよね。
澤田 あれも戦略ですよ。ビル・ゲイツの戦略勝ちですよね。
坂東 まあ確かにその辺になると社会との接点が非常に重要になってくるのですが、放射線防護において、社会との接点をあんまりにも重視したせいで、科学者が市民に寄り添うあまり、科学の本質を明確にするという任務がゆがめられる例もありますね。例えばICRPとUNSCEARがあるじゃないですか、ICRPとUNSCEARのメンバーがほとんど同じなのはおかしい、つまりUNSCEARはサイエンスでどこまで分かっているのかをハッキリさせるべきですよね。ICRPはポリシーと関係してその指針を提案するところなのに、サイエンティストだけで委員会を構成していいのかなと思います。そもそも、市民のまえにまで、サインティストが表にたって、政策をさも自分が決めたかのように話すなんてのはナンセンスだと思いませんか。市民との対話の中に科学者が入っていくのはいいのですが、本来なら行政関係の方とか政策を決定する側が責任を持ってやるべき仕事に、科学者が矢面に立つようなやり方はおかしいです。政策には、科学的根拠に基づいているとはいえ、そこにはポリシーが入ってくるんだから防護との関係できちんとそこは切り分けるべきなんですよ。さらに言えば、UNSCEARは純粋な科学的視点から現状を把握するのが任務です。当然、ICRPとはメンバーが違います。そのことをパリ会議ではポスターセッションで訴えたんですけどね。「賛成だね」と言っていくれる人もいるのですが・・・。それに、考えてみたら、ICRPのメンバーは、昔はミュラー(※1)とかニール(※2)とかラッセル(※3)とか、つまり超一流の現場のサイエンティストが入っていたわけですよ。いまのICRPはどうなんですかね?そういう人らが1ミリシーベルトがどうとか言って、言い訳するより、そこをきちんと分けるのが大切なのではないかなと思います。今回行われた2017年のパリで開かれた国際会議(※4)に出席するのに、ポスターセッションに5本申し込みました(仲間たちと共同です)が、その一の1つがオーラルトークに選ばれたのです。
※1 Hermann Joseph Muller 米国の遺伝学者、1946年ノーベル生理学・医学賞を受賞
※2 James Van Gundia Neel 米国の遺伝学者
※3 William L. Russell 米国の放射線生物学者、The Oak Ridge National Laboratory
※4 ICRP symposium & ERPW、October 10-12, 2017, Paris
澤田 日本にも、菅原務(※1)とか近藤宗平(※2)などいたのですが、どうなんですか?
※1 菅原務 医学者、京都大学名誉教授、京都大学医学部放射能基礎医学教室初代教授。同放射線生物研究センター長、同医学部長、国立京都病院院長などを歴任
※2 近藤宗平 遺伝学者、大阪大学名誉教授。大阪大学医学部放射線基礎医学教室教授、近畿大学原子力研究所教授などを歴任
坂東 どうも、日本の放射線防護の研究は、「被害を受けた」ところから出発している。そういう研究所のあるのは、広島、長崎、福島だけなのです。あとあるのは放医研(量子科学技術研究開発機構放射線医学総合研究所)ですが、ここはビキニと関係してできたんですね。それとは質を異にするのが、国立遺伝学研究所です。近藤宗平や菅原務は、基礎科学的なところから研究するという、いわば、湯川先生の構想とマッチしたところといえば、この先生方のグループでしょうね。その意味では、国立遺伝学研究所とか大阪大学はユニークです。
澤田 アリストテレスの〝事故の中に未来がある〟ということを実践できていない。 まあ要するに行政の下請けみたいになっているのですかね。
坂東 そうかもね。そうなると、言われてやっていることが多くなります。福島の健康調査も、ワイズさんは「コホート調査でもないし、ケースコントロール調査でもない、学問的には価値が低い」といわれます。UNSCEARは、学問的に価値があるのは、コホート調査、そしてケースコントロールで、それ以下は取り上げていないようです。価値がないってことですね。チェルノブイリの歴史を見ていると、事故後数年を経て国際会議が開かれ、そこで、甲状腺がんの発生の事実が問題となり、国際的に取り組もうという話がまとまってわけです。
こうした歴史を踏まえると、日本が何をすべきか明白なんですが・・・。3・11直後に物理学者たちが「すぐに放射線量を測るべきだ」と声をかけたときも、なかなか動かなくて、大阪大学が中心になって、全国の研究者に呼びかけ、大規模な線量調査をしたのですが、あまり知られていないようですね。この調査は貴重なデータを提供したんですが、JAEA(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構)に組み込まれてしまいました。
澤田 JAEAはね、一言で言えばエキスパートの集団ですね。ご下命の元にはしっかり仕事をされると思いますよ。問題はその先に踏み出せるかどうかです。
坂東 いや、当初、物理学者だけで始めたこの調査には、途中からJAEAが参入したそうですね。阪大から始まった物理屋さんたちは、土を全部持ち帰って調べてきちんと客観的に確立したデータを出すのに、科学的処方をしっかり押さえたんですが、その後、いったいどういう結果を出したのか、知りません。
澤田 そうですか。国家の予算と人員を使ってやったことでしょうから、広く国民にちゃんと還元されないといけないでしょうね。
報告書や論文を書いても、それでは人々には伝わらないですからね。そこは専門家が専門家として得た知見や情報をどのように生かしていくかという社会へ向けての責任のあり方が不明瞭なのかもしれません。
坂東 うーん、そうなんですよねぇ。科学者や専門家の社会的責任という問題は、市民などのステークホルダーといかに関わり合いを持っていくかということですね。社会との接点が、あるいは接し方が非常に重要になってくる分野、例えば低線量の放射線被ばくの影響の問題、はもしかしたら科学だけでは解決できないところがあるのかもしれないとちょっと気になっています。
もちろん私は、科学の問題は科学者が責任をもってしっかり決着がつけられるべきだ、それをおろそかにしては科学者ではないのではないかという思いを強く持っていますけどね。
澤田 アルヴィン・ワインバーグ(※1)のトランスサイエンスの問題ですね。政治や政策の意向を無視できない。といいますか、影響されずには済まされない。私は3・11後、亡くなられた長瀧重信先生(※2)はじめ多くの方々と対話をしてきました。そのなかではっきり自覚したことは、低線量被ばくの人体への影響の科学とは別の価値軸が放射線防護の世界にはあるということです。
放射線防護は、科学というよりはこうしましょうという〝方針〟ですね。ですからそこには何らかの割り切りがある。元をたどれば、日本では、武谷三男(※3)が〝がまん量〟と呼称した本来ならあびなくても良いはずの余計な被ばくをどう捉えるかという問題であり、それにまつわる〝方針〟です。
日本には放射線防護の学会があるのですが、なぜか保健物理学会と称しています。保健物理といえばなんとなくサイエンスっぽいのですがね。サイエンスで落とし所がない部分を保健物理の人たちがどう考えているのかは、私にはよく分かりません。
※1 Alvin M. Weinberg 米国の核物理学者、The Oak Ridge National Laboratory 所長などを務めた
※2 長瀧重信 医学者、長崎大学医学部長、放射線影響研究所理事長、国際被曝医療協会会長などを歴任
※3 武谷三男 理論物理学者。戦時下では理化学研究所で原子爆弾の開発(二号研究)に関わり、戦後は立教大学教授
坂東 私はやはり科学で解決できるところが低線量被ばくの問題にあるという考え方です。アルビン・ワインバーグは、科学的判断と政治の判断が少し混同しているように見えます。論理があいまいで、すっきりしないところがあるので、一度じっくり議論したいですね。
澤田 坂東さんの科学で解決できるという見込みは、例の〝もぐらたたきモデル(WAMモデル)〟に現れていますね。
坂東 ええ、確かにあれはその一つの典型例なんですが、放射線の生体リスクの歴史を辿ってみると、もっと明確にできたはずのことが、いまだにすっきりしないまま、くすぶっていることを感じます。それが政治の影響なのかどうか、科学者の見る目がなかったという面や、それをきちんと科学のモデルにしなかった責任はやっぱり科学者にあると思われるのです。政治の問題は抜きにして・・・。ですから、「科学でわからない問題」という中身は、科学者の努力によって解明していく、それが科学の本質だという意識がなければいけないと思うのです。しかし、それが希薄なのではないかという気がしています。
その意味からも、そのトランスサイエンスの問題は近頃非常に気にはなっていますので、次回はそこからはじめませんか?
澤田 いいですねえ。 今から何を話そうかと、少しワクワクしてきました。
(第2回に続く)
対談日:2017/12/5
対談場所:東京工業大学
インタビュアー:坂東 昌子
編集:坂東 昌子、角山 雄一